
○ 浅草富士通り(表参道)
○ アニマル浜口トレーニングジム
○ 富士公園
○ 富士小学校
○ 浅草警察署(旧象潟警察署)
○ 浅草富士浅間神社
○ 浅間神社〜紙洗橋
浅草観音堂裏交差点から浅草富士浅間神社に続く通りで、表参道です。
表参道から最初に交差する道を左に行くとすぐ、アニマル浜口トレーニングジムがあります。
表参道を進むと、左手に、富士公園、浅草警察署(旧象潟署)があり、
右手に富士小学校、交差点過ぎた右手に浅間神社があります。

「気合いだ〜!」
柳通りに、浜口京子さんの功績を讃えた記念樹があります。
トイレが富士山です。
富士小学校は、明治中期に廃寺となった浅草寺支院「修善院」の跡地です。
修善院は、浅草富士浅間神社を管理していました。
富士塚からは、浅草警察署が立ちはだかって、富士山は見えません。
浅草神社が社務を兼ねています。
<様々な呼称>
「浅草不二」「不二権現」「浅草田んぼの富士権現」「浅草砂利場の富士」「六郷富士」
「象潟富士」「お富士さん」「浅草富士せんげん」「浅草富士浅間宮」と、色々な呼称が見られます。
江戸切絵図では不二権現と記されています。
<六郷家が勧進>との説あり
「十方庵遊歴雑記 二編 巻之下 第十九 浅草富士せんげんの例祭」によると、
象潟の六郷家から、江戸の六郷上屋敷内に勧請したものとのこと。
邸内社でしたが、庶民が参詣できるよう小道をつけて独立させ、一般開放したのが富士せんげん。
参道には六郷家の足軽が警備していました。
富士せんげんの東のうら通りは、浅草砂利場でした。
(浅草神社の由来の説明は別の内容となっています)
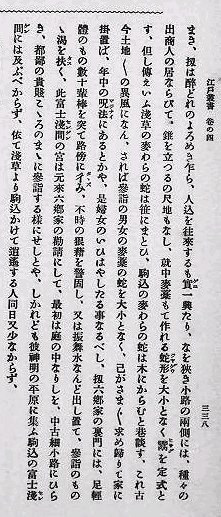
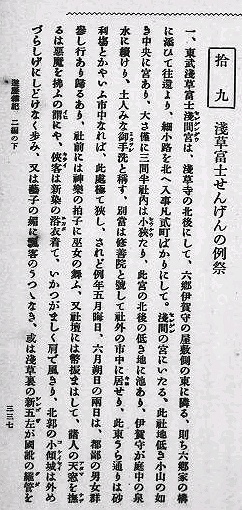
<浅間神社/浅草富士浅間神社と三好町>
(説明板)
「浅間神社(浅草のお富士さん・台東区有形民俗文化財)
台東区浅草五丁目三番二号
浅間神社は、富士山への信仰に基き勧請された神社で、神体としで「木造木花咲耶姫命坐像」を安置する。
創建年代は不明だが、『浅草寺志』所収「寛文十一年江戸絵図」に表記があり、江戸時代初期の寛文十一年(一六七一)までには鎮座していたようである。現在の鎮座地は、約ニメートルほどの高みを成しているが、中世から江戸初期にかけて、関東地方では人工の塚、あるいは自然の高みに浅間神社を勧請する習俗があったとされており、当神社の立地もそうした習俗に基くものと思われる。
江戸時代には浅草寺子院修善院の管理のもと、修験道による祭祀が行われ、江戸を代表する富士信仰の聖地として、各所の富士講講員たちの尊崇を集めた。明治維新後は浅草寺の管理を離れ、明治六年には浅草神社が社務を兼ねることとなり、現在に至っている。
本殿は、平成九・十年の改修工事によって外観のみ新たに漆喰塗がほどこされたが、内部には明治十一年建築の土蔵造り本殿が遺されている。さらに、この改修工事に伴う所蔵品調査により、江戸時代以来の神像・祭祀用具・古文書などが大量に確認された。
これら、本殿・諸資料群・境内地は、江戸時代以後の江戸・東京に
おける富士信仰のありさまを知る上で貴重であり、平成十一年三月、台東区有形民俗文化財に指定された。
祭礼は、毎年七月一日の「富士山開き」が著名でまた、五・六月
の最終土・日曜日には植木市が開催されている。
平成十二年三月 台東区教育委員会」
「浅草富士浅間神社と三好町
富士の山に似た小高い丘に勧請されたとされる当社は、元々は現蔵前の地である旧浅草三好町十番地に富士権現として鎮座されていたが、江戸時代元禄年間(一六八八〜一七〇三)に幕府の命により現在の地に遷座されたと云われている。
この三好町とは、『新選東京名所図会 浅草区之部』に「浅草三好町。東は駒形河岸の南端に接し、西は電車路線を隔てて黒船町の一部に八幡町の一部に対し、南は南元町の北端に面し、北は黒船町の一部に隣れり。地勢は平夷にして。土地の番号は一より十に至る。」と記されており、現在の蔵前二丁目周辺と考えられる。
更に同書に依れば、「三好」とは「 船首 ( みよし ) 」からの当て字とされており、この地一帯が地域における重要な御厨河岸であった事を表しているのであろう。
旧三好町自体は、時代の趨勢によりその名称が途切れているが、元禄年間以前からの同権現社の氏子であり、現在地へ遷座以降も、永きに亘り同じく当社の氏子として御祭礼に奉仕されると共に、今も尚その護持運営に格別なる御尽力を頂いている。」
<小林一茶ゆかりの地>
江戸時代、本物の富士山に代えて、不二講がたくさんあったといいます。
浅草寺の裏通りにある「背戸(裏口)不二」もその一つでした。
文化2(1805)年6月1日、小林一茶は浅間神社を参詣しています。
浅草田んぼの富士を「青田」の風が「吹過る」と一茶がよんでいます。
「背戸(の)不二青田の風を吹過る」(小林一茶)
「一茶の俳句データベース」から、浅草富士で検索すると、こんなにヒットします。
背戸(の)不二青田の風の吹過る 浅草富士詣 文化句帖
文化2
涼風もけふ一日の御不二哉 浅草富士詣 文化句帖
文化3
涼風はどこの余りかせどの不二 浅草富士詣 文化五六句記
文化6
蟷螂が不二の麓にかゝる哉 浅草富士詣 文化五六句記
文化6
不二の草さして涼しくなかりけり 浅草富士詣 文化五六句記
文化6
またぐ程の不二へも行かぬことし哉 浅草富士詣 文化五六句記
文化6
涼しさや五尺程でもお富士山 浅草富士詣 七番日記
文化11
涼しさは五尺程でもお富士也 浅草富士詣 句稿消息
文化11
涼しさは五尺そこらもお富士哉 浅草富士詣 句稿消息
文化11
富士の気で鷺は歩くや大またに 浅草富士詣 句稿消息
文化11
富士の気で跨げば草も涼しいぞ 浅草富士詣 七番日記
文化11
明ぬ間に不二十ばかり上りけり 浅草富士詣 八番日記
文政4
三尺の不二浅間菩薩かな 浅草富士詣 八番日記
文政4
涼しさや一またぎでも不二の山 浅草富士詣 梅塵八番
文政4
踏んまたぐ程でも江戸の不二の山 浅草富士詣 文政句帳
文政7
涼しさや一人又来ても不二の山 浅草富士詣 八番日記
文政4
涼しさやまたぐ程でも不二の山 浅草富士詣 書簡
蝸牛ともども不二へ上る也 浅草富士詣 文政句帖
文政6
蝸牛気永に不士へ上る也 浅草富士詣 文政句帖
文政8
蝸牛そろそろ登れ富士の山 浅草富士詣 文政版
浅草や朝飯前の不二詣 浅草富士詣 文政句帖
文政7
浅草や犬も供して不二詣 浅草富士詣 文政句帖
文政7
<富士塚 浅草富士>
平成28(2016)年6月の建立です。
5合目から登りはじめ、6合目〜9合目を過ぎ、頂上です。あっという間。
奥宮は富士山の方向ですが、浅草警察署しか見えません。
<植木市>
「お富士さんの植木市(浅間神社)
「お富士さん」と呼ばれ親しまれている浅間神社のお山開きに合わせて行われる植木市。植木屋数百軒が、浅間神社周辺に集まり、まさに夏を緑一色に彩る風物詩としても楽しい市である。」
富士通りは浅間神社への表参道で、道は浅間神社までででしたが、
現在は、浅間神社横から紙洗橋交差点まで通じています。
浅間神社から紙洗橋交差点に向かって進むと、右手に今城材木店、鶴の湯(銭湯)があり、
袖摺稲荷神社の脇を通り、紙洗橋交差点に至り、ここで土手通りに出ます。
紙洗橋交差点手前の右手(田町1丁目)が砂利場です。
・今城材木店 台東区浅草5-43-4
・鶴の湯 台東区浅草5-48-4
・袖摺稲荷 台東区浅草5-48-9
・紙洗交差点